
はーい(^O^)/Ulalaです!今日は、18~19世紀ごろのフランスの子育て事情だよ!
前回は、外国人が見た19世紀あたりの日本の赤ちゃん、子供の扱いを書きましたが、

今回は、フランスの18世紀~19世紀の赤ちゃんの扱い事情です。
フランスの子育て事情は、当時の日本とはまったくかけ離れたものでした。
フランスの乳児の子育ては乳母の仕事
16世紀ぐらいから貴族の間で乳母が子供たちの面倒をみることが定着していきました。そして17世紀に入りブルジョワの間にもその習慣が浸透し、18世紀に入ると庶民の間にも浸透!
それでも、まだまだ田舎では割と自分で自分の子供を見る家も多くありましたが、パリなどの大都市ではほとんどの人が子供を乳母に預けていたのです。
子供は、手がかからなくなるまで預けられてので、6歳~7歳までは親の手を離れていたといいます。しかも、住み込みの乳母出や、近郊に預けているのは無い限り、遠くの田舎に預けている場合は、帰ってくるまでほとんど自分の子供を見ることもありませんでした。
当時、どのぐらいの子供がパリから里子にだされていたかというと、
1780年には1年間に生まれるパリの子どもの数は2万1000人でしたが、
そのうち、
住み込みの乳母に育てられるのが1000人
母親の手で育てられるのが1000人
それ以外の子供たち、
1万9000人が里子に出されていたのです!
パリの子供の90%!!
階層ごとにわかれる預け先
預け先は、だいたい階層ごとに分かれていました。(もちろん、例外の家庭もあるので絶対とはいいきれません)
金持ちの貴族・ブルジョアは、住み込みの乳母が面倒をみました。
身元確認は確実にされていましたが、農村部から乳母になりたいという人がこぞってきており、乳母を見つけるには困らなかったようです。
住み込みの乳母に育てられる全体の約5%である1000人とは、この階層の子供だったと言えます。
こちらは、貴族に雇われた乳母。当時の子供はぐるぐる巻きにされていました。(画像はwiki乳母より)

プチ・ブルジョア、中流家庭では、パリなど都市近郊に里子に出します。
自宅に乳母を住みこませるまでの余裕はないので、私設の斡旋所から紹介を受けた乳母に里子に出しました。預け先は、都市近郊の乳母の家。
1821年に、官営乳母斡旋所には医師が乳母斡旋所に常駐するよう定められるなど管理が始まると、お金のやりとりまで厳しく取り締まるようになっため、以前からいる乳児の運び屋が私設の斡旋所を作ったのです。
私設の斡旋所の運び屋は今までのノウハウで都市近郊の割と良質な乳母を集めてくるので、プチ・ブルジョアは官営乳母斡旋所を使用したり、私設の斡旋所を使用するようになっていったのです。
また、私設の斡旋所で斡旋されると料金ももらえますが、アルコールなどの間接的報酬ももらえるので、私設の斡旋所に登録する乳母の方が多かったようです。『ボヴァリー夫人』では、都市近郊の乳母の家に預けていて、子供を見に行く描写もありますが、そこでも間接的報酬をねだっている乳母の様子が書かれています。
貧困層の庶民は、田舎に里子に出します。
官営乳母斡旋所を通して、田舎の乳母の家に里子に出しました。
官営乳母斡旋所はすっかり私設の斡旋所にとってかわられました。1821年には5000人を越えていた登録乳母の数は、1828年には激減し2000人を割ってしまいます。
それと共に、田舎のすむあまり人気のない、最低の乳母しか集まって来なくなり、官営乳母斡旋所は、主に庶民の層が利用する斡旋所になっていきます。
さらにもっと貧困層は、自分の手で育てるか、捨て子
母親の手で育てられるのが1000人の大多数がこの貧困層に含まれています。各層にも母乳で育てていた母親もいたと思いますが、この層がほとんどでした。
しかし、育てるのが無理な場合は、放置か、捨て子しました。捨てられた子供は、生まれた子供の人数としても登録されてない子供も多かったので、正確にはどのぐらい居たかは表に出てこない数字なのかもしれません。
赤ちゃんではないですが、ヴィクトル・ユーゴーが1862年に書いた小説『レ・ミゼラブル』の中にもガヴローシュと言う親に家内放置された末、浮浪児になった子供がでてきます。親がちゃんと面倒を見ないので、
当時、路上には、そういった浮浪児が多かったそうです。
偶然自分の父親が刑務所から出るのを手伝ったけれども、父親や、子供の顔も覚えておらず、息子だとも気づいてもらえなかったという悲しさ。そんな路上生活でも陽気に生き、そこで知り合った人達とともに、子供でありながら大人と一緒に革命に参加していくのです。そして。。。
捨て子の行き先
子供の放棄は18世紀に大幅に増加しました
1770年にはパリだけで7000人の孤児が居たと言います。
子供は、貧困による放棄もありますが、望まぬ妊娠や、登録されていない子供の放棄などもありました。
一八六〇年に廃止されるまで、パリのアンフェール街には、捨て子を専門に預かる棄児院という施設で、匿名での受け入れを行っていました。
しかし、捨てられる子供たちは大抵ひどい健康状態で、収容後の5日以内に4分の1が無くなり、一か月後には3分の2が息を引き取ったといいます。
1828年の統計によれば、収容人数5721人に対して、4095人が亡くなっています。約72%が亡くなったのです。
そこで生き残った子供は、公共救済児童として、パリ市が養育費をつけて最低層の乳母たちに引き取られました。お金欲しさに、中には20人もの子供を引き取る乳母もいたのでした。
農村地区はほぼ自分の手で育てる
上記の話は、あくまでもパリや都市部での話ですが、しかし、当時のフランスの80%は農村部で、農村部では大抵は子供は自分の手で育てていました。
しかしながら、中には都会に乳母として働きにいく女性もいました。子供を産んですぐ自分の子供は乳母に預け、都会に旅立っていったのですが、その方が、自分の子供を預けても働きに行く方がはるかにお金が入ってきたのは間違いありません。産んだら自分の子供は預けて働きに行くことを続け、次々と12人も子供を産み、最後には、夫に畑までプレゼントしてしまう女性もいたのがすごい!
一方、避妊もできず次々に生まれる子供、農村部では、禁止されていたのにもかかわらず、子殺しも行われていたようです。しかしながら、子殺しは秘密裏に行われていたため、具体的にどのぐらいいたのかはわかりません。
そんな、歴史の表舞台に出てこない話が、表にでてきたことがありました。フランス・アルペン地方の城で、床板の裏に大工が書き綴っていた秘密の日記が見つかったのです。当時の城主の依頼で床板を張った大工ジョアシャン・マルタン(1842年~1897年)通常の歴史資料ではとうてい知ることの出来ない、農村人間関係の実態を垣間見ることができます。
最も衝撃的な内容は赤ん坊殺しについだ。ジョアシャンは明らかに12年間、この事件を忘れられずにいた。
「1868年の真夜中、馬小屋の扉の前を通りかかると、うめき声が聞こえた。旧友の愛人で、出産の真っ最中だった」
日記によると、この女性は6人の子どもを生み、そのうち4人を馬小屋に埋めた。ジョアシャンは赤ん坊を殺したのは母親ではなく、父親で自分の旧友のベンジャミンだとはっきり書いている。そのベンジャミンは、今度は自分の妻に言い寄っているのだと。
ジョアシャンは度重なる赤ん坊殺しにぞっとしつつ、当事者を非難しない。自分とベンジャミンの家族は隣人で、しかも両家には親密な関係があるからだ。赤ん坊殺しはもちろん犯罪だが、避妊具が普及する以前は、珍しいことではなかったのかもしれない。
ジョアシャンの日記からは、レ・クロットのような農村地域で赤ん坊殺しがタブーだったことが伺える。誰もが知りながら口をつぐんでいたのだ。

こんなタブーは、田舎には結構あったんでしょうね…
「里子が全盛期だったフランスの18世紀~19世紀」前編のまとめ
・子供を預けることができない都会の最貧困層は、自分で育てるか、捨て子した
・農家では、自分で育てるのが主流。
・表に出ない子殺しもあった。
日本も、貧困層では捨て子や子殺しがあったのは同じだと思いますが、この時代のフランスは、ほんとうに親が子供を育てるのは都会ではほんの少数だったことにとても驚かされます。
おんぶされて家族といつも一緒に成長していった日本の子供たちとはほんとうに違う人生を歩んでいましたね。
フランス編の後編では、里子に出された子供の運命についてさらに驚きの事実と、なぜ女性が子育てをしなかったかの理由がでてきますのでお楽しみに。
明日は日本編の後編。でわでわ、また明日~(^^♪


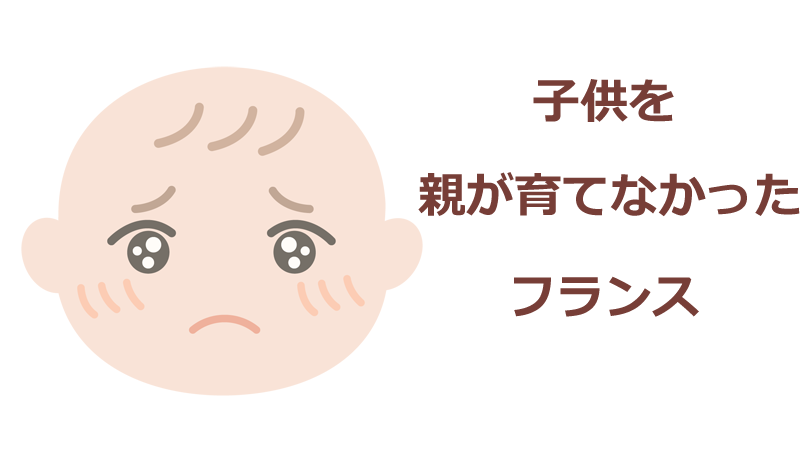



コメント
日本の昭和の頃も板橋で『岩の坂事件』という似たような事件がありました。
中絶は技術的にも法的にも難しかったので、出産後に斡旋所に手数料と養育費を付けて養子に出し、そこを利用して30人以上を引き取っていたグループが赤ん坊が1人を除く全員を変死させていた事件。
佐賀では60人以上、新宿では100人以上も同様の手口での変死が横行していたそうです。
当時は倫理的な事情も厳しく避妊技術も無かったので、主に子供の母親はお金が払えるくらいの良家の子女が多かったそうです。
(当時新しく入ってきた”恋愛”の概念全盛期だったので、恋愛絶食の現代とは少し事情が違います)
都市部の急激な人口増加と大恐慌の煽りで街がスラム化した事と、当時は福祉制度が十分で無かった事も原因。
どこの世界でも急激な都市化で犠牲者が出るのは一緒ですね。